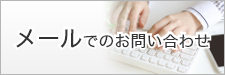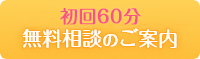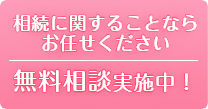2024年11月05日
Q:父の遺産相続について、遺産分割協議書を作る必要はあるのでしょうか。行政書士の先生に教えていただきたいです。(豊田)
豊田市在住の主婦です。遺産相続について判断が難しいことが多く、行政書士の先生に質問させていただきました。先日、豊田市内の病院に入院していた父が亡くなりました。父は長いこと闘病しており、私たち家族はある程度覚悟をしていました。葬儀や遺産相続についても、生前父から大体のことは聞いていました。遺言書はなく、父から口頭で聞いた通りに遺産相続を進めています。父の遺産は預貯金が数百万と豊田の自宅のみのため、相続人全員で一度話し合いをしようと思っています。話し合いはスムーズに終わりそうなので、遺産分割協議書を作成する必要はないかと思いますが、作成する必要はあるのでしょうか。(豊田)
A:相続手続きや今後のトラブル回避のために遺産分割協議書は作成しましょう。
遺産分割協議書は、相続人全員が遺産分割協議で合意した内容を書面にまとめたものです。遺言書がある場合には、遺言書の内容に従って遺産相続を進めるため、遺産分割協議および遺産分割協議書の作成も必要ありません。遺言書がない場合には、遺産分割協議で決まった内容で遺産相続を行うため、協議書を作成しましょう。仲の良い間柄であっても、遺産相続は大きな財産が手に入ることになるため、トラブルになるケースも少なくありません。スムーズに話し合いを終えたとしても、後々相続人同士でトラブルになった際に、書面に合意した内容を記しておくことで遺産分割協議時の内容を確認することができます。
また、遺言書がない場合には、不動産の名義変更の際に遺産分割協議書が必要になります。
したがって、相続人全員が集まって話し合いをする遺産分割協議の際に、遺産分割協議書を作成するようにしましょう。
【遺言書がない遺産相続で遺産分割協議書が必要となる場面】
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 相続税の申告
- 金融機関の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書がない場合、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
- 相続人同士のトラブルを回避するため
相続は何度も経験することではないため、不慣れな手続きや判断が難しい手続きがあるのは当然です。遺産分割協議では、相続人間で争いに発展してしまうケースもあります。ご自身だけで解決するには難しいことも、相続の花笑みの相続の専門家に一度ご相談いただけないでしょうか。相続の花笑みでは相続の専門家が豊田の皆様の相続手続きを親身にサポートいたします。豊田で相続手続きの専門家をお探しの方は相続の花笑みにお任せください。まずは初回の無料相談をお気軽にご利用ください。
2024年10月03日
Q:父の相続手続きに着手しました。戸籍収集について行政書士の先生に教えていただきたいです。(豊田)
豊田で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。母は既に他界しており実子は私のみになるため、相続人は私のみになると思います。父名義の預貯金口座について手続きを進めようと銀行の窓口へいったところ、書類が不十分と言われ、手続きができませんでした。私が準備した書類は、父の死亡が分かる戸籍と私の現在戸籍です。父の相続手続きを進めるには、他にどの戸籍が必要なのでしょうか。また、請求方法についても教えてください。(豊田)
A:相続手続きで必要な戸籍は被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人の現在戸籍です。
相続手続きでは基本的には下記の戸籍を用意しましょう。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集することにより、被相続人の両親が誰か、兄弟姉妹はいるのか、死亡時に配偶者はいるのか、いる場合配偶者は誰か、子供は何人いるか、亡くなったのはいつかという内容をすべて確認することができます。この戸籍によって、ご相談者様が把握されていない認知している子や養子がいることが分かった場合、相続人はご相談者様だけでなく、その方も相続人になります。したがって、相続が発生したら早めに被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を収集し、相続人を確定するようにしましょう。
これらの戸籍は、一か所の市区町村窓口に請求することによって揃えることができます。これまで、被相続人の出生から死亡までの戸籍収集は過去に戸籍が置かれていた市区町村すべてに請求する必要がありましたが、2024年3月1日の戸籍法の一部改正により、戸籍の広域交付が開始されたことから、本人、配偶者、子、父母などであれば一か所でまとめて請求できるようになりました。なお、兄弟姉妹や代理人は広域交付を利用することができません。
戸籍は複数種類があり、初めての相続では戸惑う方がほとんどです。相続では戸籍の収集以外にも多くの手続きがあります。中には期限が設けられている手続きもありますので、まずは相続人の調査から早めに着手するようにしましょう。ご自分での手続きがご不安な方は、相続続きの専門家に依頼することも可能です。豊田で相続手続きのご相談なら相続の花笑みにお任せください。相続の花笑みでは豊田エリアで相続手続きの実績豊富な行政書士が豊田の皆様の相続手続きを親身にサポートさせていただきます。まずは初回の完全無料相談をご活用ください。豊田の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。
2024年09月03日
Q:行政書士の先生、両親が連名で遺言書を作成したようなのですが、問題ないのでしょうか?(豊田)
遺言書のことで疑問がありご連絡しました。先日、豊田の実家に帰省した際に、相続の話が出ました。私の両親はまだ健在で、豊田の実家で2人仲良く暮らしているのですが、万が一の時に備えて遺言書を作成したのだと言います。遺言書は豊田の実家の金庫内に保管しておくので、両親のどちらかが亡くなった際は確認するように、と言われました。
現在両親が暮らしている豊田の実家は父名義ですが、母も昔から豊田に暮らしており、曾祖父の代から相続している母名義の土地があるので、2人の財産の分割方法について両親で話し合い、連名で遺言書を作成したそうです。
そこで疑問に思ったのですが、1つの遺言書を2人で作成しても問題ないのでしょうか?遺言書を作成してくれたのは大変ありがたいのですが、もし問題のある遺言書だと困るので、念のため確認させていただきました。(豊田)
A:民法では共同遺言を禁止していますので、連名で作成した遺言書は無効となります。
ご夫婦で一つの遺言書を作成したいというご要望をいただくこともありますが、民法では共同遺言の禁止を定めていますので、残念ですが複数名で一つの遺言書を作成することはできません。もしも一つの遺言書に複数名の署名がなされている場合には、その遺言書は無効となってしまいます。
遺言書は、遺言者の最終意思を相続人に伝える書面であり、そこに記された内容は本人の自由な意思を反映させたものでなければなりません。複数名で作成してしまうと、誰か一人が主導的に作成し、他の人の意思は反映されていないのではないか、という可能性を否定できないのです。
また、作成した遺言書を撤回したいとき、複数名で作成していた場合は全員の承諾を得る必要が出てきます。これでは遺言書の撤回の自由を奪われていることと同義といえます。
このような理由から、遺言書は複数名では作成できないことになっているのです。
遺言書の作成にはさまざまなルールが設けられています。ご自身で作成する自筆証書遺言は、費用もかからず手軽に作成することができますが、その遺言書が法的なルールから逸脱している場合は無効となり、相続手続きに使用することができなくなってしまいます。せっかく作成した遺言書が無効にならないよう、しっかりとルールを確認してから作成することが大切です。
相続の花笑みは相続・遺言書に精通した行政書士事務所で、豊田の皆様の遺言書作成サポートも承っております。初回のご相談は完全無料ですので、ぜひ相続の花笑みまでお気軽にお問い合わせください。
2024年08月05日
Q:行政書士の先生、今回の父の遺産相続おける法定相続分の割合を教えてください。(豊田)
このたび豊田の病院に長らく入院していた父が亡くなりました。遺言書はありませんので、これから遺産相続について相続人同士で考えなければならないのですが、遺産分割にあたり法定相続分の割合を確認したく、ご連絡いたしました。
今回の父の遺産相続において、相続人となるのは母、私、妹の2人の娘、以上4人です。実は妹は父が亡くなるよりも前に他界しておりますので、妹の2人の娘が相続人となります。
相続関係がやや複雑になることもあり、後々のトラブルに発展させないためにも、法定相続分の割合に沿った遺産分割にしたいと思っています。行政書士の先生、このような場合の法定相続分の割合について教えてください。(豊田)
A:遺産相続の相続順位に応じた法定相続分の割合についてご案内いたします。
法的に相続権を有すると認められた者を「法定相続人」といいます。民法では相続順位を定めており、それにより誰が法定相続人になるのかを確認できます。そして法定相続分は、相続順位に応じて割合が定められています。まずは相続順位について確認しましょう。
【相続順位】
- 配偶者は常に法定相続人
- 第一順位:直系卑属である子(孫)
- 第二順位:直系尊属である父母(祖父母)
- 第三順位:傍系血族である兄弟姉妹
配偶者はいかなるときでも法定相続人に該当します。その他については、第一順位の該当者が存命の場合、下位の該当者が法定相続人となることはありません。上位の該当者がいない場合(死亡している、相続放棄した、そもそも存在しないなど)、次点の順位の該当者が法定相続人となります。
豊田のご相談者様のお話から、今回の遺産相続ではまずお母様が法定相続人となり、ご相談者様と妹様の2人のご息女はともに第一順位の法定相続人に該当します。
次に法定相続分の割合ですが、以下の民法上の定めをご覧ください。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
上記を踏まえて計算しますと、まずはお母様の割合が1/2となります。そして残りの1/2を子であるご相談者様と妹様で分け合いますので、ご相談者様の割合は1/4となります。そして妹様の2人のご息女については、妹様の1/4を2人で分け合うことになりますので、ご息女1人あたりの割合は1/8となります。
以上が法定相続分の割合となりますが、遺産分割協議にて相続人全員が納得すれば、基本的には自由な割合で遺産分割することも可能です。
豊田の皆様、法定相続分の割合については、遺産相続の状況によって異なってきます。相続の花笑みにご相談いただけましたら、豊田の皆様のご家庭の状況を整理したうえで、法定相続分の割合や必要となる遺産相続手続きについて、丁寧にご案内させていただきます。初回のご相談は完全無料ですので、豊田の皆様の遺産相続についてはどうぞお気軽に相続の花笑みまでお問い合わせください。
2024年07月03日
Q:行政書士の先生、相続手続きにはどのくらいの期間がかかると見込んでおけばよいでしょうか。(豊田)
豊田で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。母は私の幼少期に既に他界しておりますので、父の相続で相続人となるのは、私と弟の2人だけになるかと思います。先日豊田に戻り、ひとまず父が暮らしていた豊田の自宅を片付けたのですが、相続財産になりそうなものといえば、銀行に預けてある数百万の現金くらいでした。あとは、豊田の自宅については父が祖母から相続したものだと聞いていますので、父名義になっているはずです。
これらの相続手続きを進めたいと思うのですが、私も弟も豊田から離れて暮らしているものですから、なかなかまとまった時間を作ることが難しいと思います。行政書士の先生、財産の相続手続きにはどのくらいの期間を見込んでおけばよいか、教えていただけますか。(豊田)
A:財産の相続手続きにかかる期間の目安をお伝えいたします。
相続の花笑みにお問い合わせいただきありがとうございます。相続手続きが必要となる財産としては、主に金融資産(預貯金、株式など)や不動産(土地、建物など)が挙げられます。他にも相続手続きの対象となる財産はありますが、今回の豊田のご相談者様のお話から、金融資産と不動産それぞれの相続手続きに要する期間の目安をお伝えいたします。
◆金融資産の相続手続き……およそ2か月弱
被相続人の口座の名義を、相続した人の名義へと変更します。あるいは、口座を解約し、現金を分け合います。この時必要となる書類は、金融機関所定の相続届、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、相続人の印鑑登録証明書などです(相続状況や金融機関によって、必要書類は異なる場合があります)。これらの書類収集から、金融機関での手続きが完了するまでに、トータルで2か月弱程度かかるのが一般的です。
◆不動産の相続手続き……およそ2か月弱
被相続人の不動産の名義を、相続した人の名義へと変更します。この時必要となる書類は、対象の不動産の固定資産税評価証明書、戸籍謄本一式、相続する人の住民票、被相続人の住民票の除票、遺産分割協議書、相続人の印鑑登録証明書などです(相続状況によって、必要書類は異なる場合があります)。これらの書類を揃えて、登記申請書と共に法務局へ提出します。書類収集から法務局での手続きが終わるまでに、2か月弱ほどかかると見込んでおきましょう。
以上が一般的な相続手続きにかかる期間ですが、相続人が自筆で作成した遺言書(自筆証書遺言)が豊田のご自宅等から見つかった場合や、相続人の中に未成年者がいる場合などは、家庭裁判所での手続きを要します。その場合はさらにお時間がかかりますのでご了承ください。
相続手続きは相続の専門家に依頼することも可能です。豊田での相続手続きなら、豊富な知識と実績を有する相続の花笑みにお任せください。初回無料相談の段階から、相続の専門家が丁寧に対応させていただきます。
行政書士法人花笑みは愛知県の専門家です
0120-547-053
営業時間 9:00~19:00(土日祝も営業)

みよし市・豊田市・豊明市・日進市を中心とした愛知県中央エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談ください。