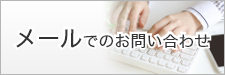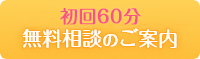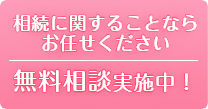2025年07月02日
Q:母の再婚相手の方が亡くなったのですが、私に遺産相続の権利があるのかどうか、行政書士の先生に教えていただきたい。(豊田)
先日亡くなった母の再婚相手の遺産相続について、行政書士の先生にお尋ねします。
私には物心ついたころから父親がいませんでした。経済的な余裕のない暮らしではありましたが、母と私と弟の3人で協力しながら豊田で暮らしてきました。そんな中、私たち家族を気にかけ、学業のことなどでよく面倒を見てくれていた人がいます。それは母の職場の同僚である男性で、豊田で母がずっとお世話になっている方です。私が成人して豊田の実家を出た後、その方と母が再婚すると聞いた時にはとても嬉しかったことをよく覚えています。私も弟も、その方を本当の父のように慕っていました。
その方が亡くなり、先日豊田での葬儀を終えました。遺産相続について、母は、私と弟にも遺産の一部を相続してほしいと考えているようです。その気持ちはありがたいのですが、血のつながっていない私と弟に遺産相続の権利はあるのだろうか?と疑問があります。行政書士の先生、私と弟は母の再婚相手の財産を遺産相続できるのでしょうか。(豊田)
A:親の再婚相手の遺産相続に関係するかどうかは、養子縁組を行ったか否かで判断します。
実の親が再婚し、その再婚相手が亡くなった場合、再婚相手の方と養子縁組を行っているか否かが遺産相続のポイントとなります。
被相続人(亡くなった方)の子で法定相続人となれるのは、血のつながりのある実子か、養子縁組を終えた養子のみです。血のつながっていない、いわゆる”義理の子”で、養子になっていない子には遺産相続の権利がありません。
豊田のご相談者様のお話から、お母様が再婚されたのはご相談者様の成人後ということがわかります。成人でも養子になることは可能ですが、その場合は、養子となるご本人ならびに養親となる方双方が養子縁組届に署名する必要があります。つまり、豊田のご相談者様が自ら養子縁組の届け出に署名をしない限り、再婚相手の方の養子になることはできないため、ご自身が養子かどうかはご自身でお分かりになるでしょう。
豊田のご相談者様や弟様が養子縁組を行ったのであれば、今回の遺産相続において相続人となります。
遺産相続にはさまざまな法的な定めがあり、各ご家庭のご事情によって行うべき手続きが大きく異なることも珍しくありません。遺産相続に関してご不明な点がある豊田の皆様は、相続の花笑みまでお気軽にお問い合わせください。相続の花笑みの初回無料相談では、遺産相続の専門家が、豊田の皆様それぞれのご事情・ご状況を丁寧にお伺いし、わかりやすく丁寧にご説明いたします。
2025年06月03日
Q:遺言書を子どもに遺し、家族間のトラブル発生を事前に回避したく、行政書士の先生に遺言書の作成方法を相談したい(豊田)
私は豊田市在住の60代男性です。今まで特に大きな病気はしておりませんが、最近体調に少し不安を感じるようになってきたのを機に、今後万が一、自分に何かあった時のため、遺言書を作成した方が良いのではないかと考え始めました。相続人は2人の子どもたち、相続対象になる財産は、豊田市内にある不動産が複数と、預貯金が少しあります。先日相続を経験した知人から、たとえ仲の良い家族でも、相続の際は揉め事やトラブルが起こる事があると伺い、まだ自分が元気でいられるうちに遺言書を作り、自分も家族も安心できればと思っております。遺言書の作成は初めてのため、何から手を付けたら良いかわからず、初歩的な部分からご教授願えませんでしょうか?自分が亡くなった後、家族がもめることなく円満な相続手続きができるよう、お力添えをよろしくお願いいたします。(豊田)
A:ご自身の気持ちを反映した遺言書を、ご健康でいらっしゃるうちに作成しましょう。
遺言書を作成することで、財産の分割内容をご自身で決める事ができます。原則、相続においては遺言書に記載された内容が優先されますので、ご相談者様とご遺族様双方が納得のいく内容を検討し、作成すると良いでしょう。
ご相談者様につきましては不動産が主な相続財産になるかと思います。特に不動産ばかりの相続の場合、たとえ日頃から仲の良いご家族でも揉めてしまうことがあります。しかし遺言書を作成しておけば、相続が発生した際に遺産分割協議を行うことなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを行いますので、揉め事やトラブルを回避できる可能性があります。ご相談者様がお元気でいらっしゃるうちに、ご自身の意思を反映した遺言書を作成し、事前に対策をしておくことで後々の相続トラブルを避けることができます。
遺言書の基本的な内容についてご説明させていただきます。
遺言書(普通方式)には、主に以下3種類があります。
- 自筆証書遺言 遺言を作成する人が自筆で作成します。手軽に費用を掛けず作成できますが、遺言の方式を守らないと無効となってしまいます。また、開封の際に家庭裁判所で検認手続きが必要となります。
※2020年7月より法務局で自筆証書遺言書を保管できるようになりました。法務局で保管された自筆遺言証書については、家庭裁判所での検認手続きは不要です。
また、どのような遺産があるのかを明らかにするための財産目録については、パソコンで本人以外の者が作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。
- 公正証書遺言 公証役場の公証人が作成します。法律に精通した公証人が作成するため、方式についての心配がなく、確実な遺言書といえます。また、公証役場にて原本が保管されるため紛失や偽造されることがなく、お勧めの遺言書ですが、デメリットとして作成に際しては費用がかかります。
- 秘密証書遺言 遺言者が内容を秘密にしたまま遺言書を作成し、その遺言書の存在だけを公証人が証明する方法です。封をして公証役場に提出するため、遺言の内容を本人以外が知ることなく作成できますが、遺言の方式の不備で無効となってしまう危険性があるため、現在はあまり使われていません。
ご自身の気持ちを反映した確実な遺言書を残したい場合は②の公正証書遺言を作成することをおすすめします。また、法的な効力はありませんが、遺言書の作成に至ったご相談者様のお気持ちや、遺されたお子様たちへの思いなどを伝えることができる、「付言事項」を記載することもできます。
相続の花笑みでは、豊田の地域事情にも詳しい専門家が、豊田にお住まいの皆様の相続のお手伝いをさせて頂きます。初回は完全無料でご相談をお伺いさせていただいております。遺言書の作成のみならず相続全般でお困りの豊田にお住まいの方は、お気軽にご相談下さい。
相続の花笑みでは豊田にお住まいの皆さまからのご相談事に対してお役に立てるよう、真摯に対応させていただいております。
2025年05月02日
Q:兄が亡くなり相続手続きを進めたいのですがどの戸籍を取り寄せる必要があるのか、行政書士の先生にお伺いしたいです。(豊田)
豊田で一人暮らしをしていた兄が亡くなりました。兄は生涯独身です。私たちの両親も他界しているため、兄の身内は弟の私のみになります。兄の相続手続きを進めようと、まずは戸籍を収集しようとしたのですが、相続手続きで必要になる戸籍についてよくわかりません。人から聞いた話によると、兄弟の戸籍を取り寄せるのは少し手間なのでしょうか。具体的に必要な戸籍について教えていただきたいです。(豊田)
A:兄弟の相続手続きには下記の戸籍が必要となります。
まず、相続手続きで必要となる基本的な戸籍は下記になります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
兄弟姉妹の相続では、上記の戸籍に加え下記の戸籍も取り寄せます。
- 被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
これらの戸籍により、法定相続人であることを第三者に証明することができます。被相続人の出生から死亡までの戸籍では、被相続人の配偶者や子の有無を確認することができます。この戸籍に被相続人が認知している子供や養子がいる記録がある場合にはその人が相続人となり、ご相談者様は相続人ではありません。
加えて被相続人の両親それぞれの戸籍ではご両親が亡くなっていること、兄弟姉妹はいるか等を確認することができます。
これらの戸籍を収集するには、被相続人の最後の戸籍からさかのぼり、出生時の戸籍まで追っていきます(兄弟相続では、ご両親の戸籍から追います)。
兄弟相続の場合、過去に戸籍が置かれていた市区町村すべてに請求する必要があるため、転籍をしている分、手間がかかります。そのため、戸籍の収集作業は早めに着手するようにしましょう。
このように、兄弟の相続手続きを行う場合、多くの戸籍を取り寄せる必要があるため、手間と時間がかかります。相続手続きは戸籍収集をはじめ相続財産の調査や相続方法の決定、財産の名義変更などまだまだ多くの手続きがあります。相続手続きは専門家に依頼することも可能です。一人で悩まずにまずはお近くの専門家にご相談ください。豊田で相続手続きのご相談なら相続の花笑みにお問い合わせください。初回は完全無料でご相談いただけます。どんな些細なことでも構いません。相続の花笑みの専門家が豊田の皆様の相続手続きを親身にサポートいたします。
2025年04月03日
Q:相続財産が不動産しかない場合はどうすべきか行政書士の方に伺います。(豊田)
先日父が亡くなり、豊田市内の斎場で葬式を行いました。相続人は私と弟二人の計3人です。父は母と離婚してから豊田の実家で一人暮らしをしていました。晩年は足腰も悪くなったためヘルパーさんが来てくれており、比較的近くに住んでいる私も時々様子を見に行っていました。弟たちは大学を卒業してからは豊田から離れていますが、男兄弟3人でも仲は悪くないと思います。父の遺産は豊田の実家と豊田郊外の空き地だけで、現金はあまりありません。このような場合、相続人3人でどうやって遺産を分けたらいいでしょうか。今のところ実家は手放したくないと思っています。(豊田)
A:相続財産が不動産だけの場合の分割方法をご紹介します。
相続が開始されましたら、まずは遺言書を探してみて下さい。相続では遺言書の有無で相続手続きの方法が異なります。遺言書が見つかった場合は、遺言書を開封して(自宅保管の場合は家庭裁判所で検認が必要)、その内容に従って遺産分割を行えばいいので面倒な遺産分割協議は行う必要はありません。こちらでは遺言書がない場合の分割方法についてご説明します。
被相続人の財産はお亡くなりになった時点で相続人の共有財産となります。そのため、そのままでは扱いにくいため遺産分割を行う必要があります。お父様のご自宅と空き地、現金は遺産分割前はご兄弟3人の共有の財産です。不動産についても今はご相談者様と弟様たちの共有の財産ですので3人揃ったうえで話し合い、遺産分割を行います。
なお、遺産分割の話し合いを始める前に、お父様のご自宅と空き地の評価を行って、その価値を明らかにしておくことをお勧めします。
【現物分割】遺産をそのまま分ける方法です。例えばAが自宅、Bが空き地、Cが現金という分け方になります。不動産評価が同じではないため、平等ではありませんが、相続人全員が納得するようであれば問題ありません。
【代償分割】特定の相続人が遺産を相続します。その他の相続人に対して法定相続分の不足分の代償金または代償財産を支払い平等とします。相続財産であるご自宅に相続人が住んでいる場合などに有効的な方法です。不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができますが、財産を相続した者は代償金として支払うまとまった額を用意しなければなりません。
【換価分割】遺産である不動産を売却して現金化し、相続人で分割します。相続した不動産が必要ないといった場合におすすめです。
相続の花笑みでは、豊田のみならず、豊田周辺地域にお住まいの皆様から相続手続き、に関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続き、は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。相続の花笑みでは豊田の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、相続の花笑みでは豊田の地域事情に詳しい相続手続き、の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
豊田の皆様、ならびに豊田で相続手続き、ができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2025年03月03日
Q:遺言書の種類について行政書士の方に伺います。(豊田)
私は豊田に住む70代自営業の男性です。子どもたちが私の相続で揉めて欲しくないので遺言書を作ろうと思っています。友人が先日遺言書を作成したらしいのですが、遺言書の事なら行政書士が専門だと聞きました。素人の私が見よう見まねで作成するより、専門家に依頼して間違いの無い確実な遺言書を作成したいと思い、先に遺言書について知っておこうと思い問い合わせました。私が死んだ場合、相続財産は豊田の不動産がいくつかと多少の預貯金です。妻と3人の子供たちが相続人のはずです。遺言書がないと相続人同士で財産の奪い合いになると聞いて、ドラマみたいなことが本当にあるんだと怖くなりました。今のうちに遺言書を作成して今後は安心して暮らしたいと思っております。円満な相続手続きのためにぜひアドバイスをお願いします。(豊田)
A:ご家族が安心できるようご自身に合った遺言書を作成しましょう。
遺言書のない相続において相続人同士で財産の奪い合いになるケースは、実際には意外とあります。特に遺産に不動産が含まれる場合には遺産の額が大きくなるため、遺産分割でもめる可能性が高くなります。このようなトラブルを避けるため、遺言書を作成してご自身の財産の分割について「誰が何をどのくらい」分けるか先に決めておきましょう。ただし、相続人が不公平になるような偏った内容にしないよう、遺言者とご遺族が納得のいく内容を検討するようにして下さい。
相続では「遺言者の最後の意思」である遺言書が原則優先されますが、遺言者がお元気なうちに作成しておく必要があります。自分の意思をしっかりと反映した遺言書となるよう専門家と相談をしながら作成する事をお勧めします。
次に遺言書の種類についてご説明させていただきますが、詳しくは当事務所の初回の無料相談で対応させていただきます。
【遺言書の普通方式3種類】
①自筆証書遺言・・・遺言者の好きな場所、タイミングで自筆で作成します。費用は掛からず手軽であるのに加え、財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。ただし、遺言書の作成方式を守らないと無効となります。なお、法務局で保管していない自筆遺言証書に関しては開封前に家庭裁判所において検認手続きを行う必要があります。
②公正証書遺言・・・2人以上の証人と共に公証役場に出向き、公証役場の公証人が遺言者から遺言内容を聞き取って作成します。原本は公証役場に保管され、遺言者には正本、謄本が渡されます。原本は公証役場にあるため偽造や紛失の心配がありません。公証人が作成するため方式についての不備もなく確実な遺言書ではありますが、費用がかかるうえ、公証人や証人とのスケジュール調整が必要です。
③秘密証書遺言・・・自筆証書遺言のように、遺言者がお好きなタイミングで遺言書を作成し封をして公証役場に持ち込み、公証人が「遺言書の存在」を証明します。封をしてから持ち込むので他人が遺言の内容を知ることはありません。しかしながら、書き方のチェックもできないため方式不備で無効となる危険性があるにもかかわらず、費用もかかるため現在はあまり使用されていない方式です。
相続の花笑みは、相続手続きの専門家として、豊田エリアの皆様をはじめ、豊田周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
相続の花笑みでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、豊田の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは相続の花笑みの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。相続の花笑みのスタッフ一同、豊田の皆様、ならびに豊田で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
行政書士法人花笑みは愛知県の専門家です
0120-547-053
営業時間 9:00~19:00(土日祝も営業)

みよし市・豊田市・豊明市・日進市を中心とした愛知県中央エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談ください。