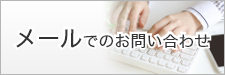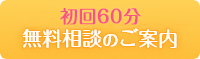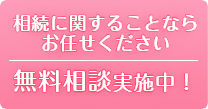遺産分割
2026年02月02日
Q:母の遺産相続に際して、弟夫婦が遺産分割協議書を作成すべきだというのですが、なぜ作成すべきなのか行政書士の先生にお尋ねします。(豊田)
先日、母が豊田の自宅で亡くなりました。母と父はずいぶん前に離婚しておりますので、母の遺産相続では長女の私と、長男、次男の3人が相続人となります。
私は母の亡くなる日まで豊田の自宅で同居しておりましたので、豊田の自宅は私が遺産相続するとして、その他の預金や細々とした財産は偏りなく分け合うということで、遺産相続の方針は固まりました。
豊田の実家は名義変更などの遺産相続手続きが必要でしょうから、早速手続きに入ろうと思ったところ、次男夫婦が「遺産分割協議書を作成すべきだ」と言いだしました。
豊田の自宅を除けばそのほかの遺産はそれほど高額でもないし、みな遺産相続の方針に納得しているのだから、わざわざ書面を作成するほどのことでもないように思うのですが、次男の奥さんは過去に別の遺産相続で揉めに揉めた経験があるらしく、遺産分割協議書は必須だと言います。
行政書士の先生、相続人がみな遺産相続に納得していたとしても、遺産分割協議書は作成しなければならいのでしょうか。遺産分割協議書がなければ遺産相続の手続きができないというならば仕方ありませんが、そもそも何のために遺産分割協議書が必要なのか、教えていただけますか。(豊田)
A:遺産分割協議書は遺産相続のさまざまな手続きで活用されるうえ、相続トラブル回避にも貢献しますので、作成をおすすめいたします。
遺産分割協議書は、被相続人(亡くなった方)が遺言書を遺していない場合に作成する書面です。
もし遺言書があれば、その中に遺産分割に関する被相続人の遺志が記されていますので、原則としてその遺言書の内容をもとに遺産相続の手続きを進めます。そのため、相続人同士で遺産分割について話し合う必要はなく、遺産分割協議書の作成も不要です。
一方、遺言書のない遺産相続では、どの遺産を誰が取得するのか、相続人全員で話し合って決定する必要があります。この話し合いを「遺産分割協議」といい、この協議で決定した事項をまとめて書面にしたものが「遺産分割協議書」です。
遺産分割協議書は、遺産分割の内容を記載したうえで、相続人全員が署名し、実印を押すことで完成します。相続人全員の署名捺印がなされることで、遺産分割協議書は「遺産分割について相続人全員が合意している」と証明する法的な書面として扱われ、遺産相続手続きのさまざまな場面で活用できるようになります。
例えば、豊田のご実家をご相談者様が遺産相続するのであれば、相続登記の申請を行い、その名義を変更する必要があります。その際、遺産分割協議書を登記申請書と共に提示することになります。
ご状況によっては相続税の申告納税義務が生じる場合もありますが、そこでも遺産分割協議書が活用されます。
また、被相続人名義の銀行口座が複数ある場合、その遺産相続手続きの際に遺産分割協議書を持参すれば、銀行所定の相続届に相続人全員が毎回署名捺印する必要がなくなりますので、手間がかからずに済みます。
その都度相続人全員が署名捺印せずとも、遺産分割協議書を提示するだけで済むことを考えれば、あらかじめ遺産分割協議書を作成しておくことは十分メリットがあるのではないでしょうか。
弟様の奥様は過去の遺産相続で揉めた経験がおありのようですが、実際のところ、遺産相続は財産が動く手続きですので、相続人同士が衝突することも珍しいことではありません。遺産相続についてみな納得したと思っていても、後になって当初と異なる意見を主張されてトラブルになるケースもあります。あらかじめ遺産分割協議書を作成すれば、このような後々の遺産相続トラブルの回避に貢献すると考えられます。
遺産分割協議書は、遺産相続の手続きを円滑に進めること、ならびに今後の安心を確保することに役立ちますので、作成されることをおすすめいたします。
豊田の皆様、遺産相続にはさまざまな手続きが伴いますので、ご負担に感じることも多いかと存じます。相続の花笑みでは、豊田の皆様の遺産相続が円滑に完了するようお手伝いしております。豊田の皆様のご状況に応じて柔軟にサポートいたしますので、まずはお気軽に相続の花笑みの初回完全無料相談をご利用ください。
2025年08月04日
Q:祖母の相続における法定相続分について、行政書士の方に伺います。(豊田)
私は豊田で暮らす30代男性です。先日、遠方で暮らす父方の祖母が亡くなったとのことで、叔父から連絡を受けました。叔父曰く、祖母の実子である私の父が既に他界しているため、代襲相続ということで私と妹が父の代わりに相続人になるのだそうです。
父が亡くなったのは私がまだ子供のころで、父が他界したのを機に母の地元である豊田に越してきました。そのため、父方の親族とはほぼ疎遠の状態です。しかし、祖母の相続において代襲相続人である私と妹にも権利があるのだから、遺産分割にもしっかり参加するつもりでいます。
そこで、まずは私たちの法定相続分の割合がどの程度になるのか確認したいと思い、相談させていただきました。今回の相続人は、叔父、叔母、私、妹の4人です。(豊田)
A:法定相続分の割合は、相続順位と法定相続分についての定めにより確認できます。
民法では、法定相続人(遺産相続の権利を有する人)と相続順位、ならびに法定相続分(各法定相続人の取得する遺産の割合の目安)を定めています。
まずは法定相続人それぞれの相続順位と法定相続分に関する民法の定めを確認し、豊田のご相談者様のケースにおける法定相続分の割合を確認しましょう。
(1)法定相続人と相続順位
法定相続人の範囲と相続順位は以下のように定められています。
- 被相続人の配偶者は常に相続人
- 第一順位:子、孫…直系卑属
- 第二順位:父母、祖父母…直系尊属
- 第三順位:兄弟姉妹…傍系血族
まず、被相続人の配偶者は常に法定相続人です。第一順位に該当者が存在する場合、第二順位以下の該当者は法定相続人ではありません。第一順位の該当者が不在の時に、次点の第二順位の該当者が法定相続人となります。第二順位の該当者も不在の場合は、第三順位の該当者が法定相続人となります。
(2)法定相続分の割合
法定相続分についての定めは、民法第900条に記載があります。以下、民法より抜粋した内容です。
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
以上を踏まえ、豊田のご相談者様の法定相続分を考えていきます。
まず、御祖母様の相続において、叔父様、叔母様、豊田のご相談者様、妹様もすべて第一順位の法定相続人となります。
ただし、法定相続分については、豊田のご相談者様ならびに妹様は、元々の相続人である亡くなったお父様の割合を2人で分け合うことになります。したがって、以下のような計算となります。
- 叔父様:1/3
- 叔母様:1/3
- 豊田のご相談者様:1/3(亡くなったお父様の法定相続分)÷2人=1/6
- 豊田のご相談者様の妹様:1/3(亡くなったお父様の法定相続分)÷2人=1/6
なお、豊田のご相談者様の法定相続分についてご説明しましたが、法定相続分は遺産分割の際に目安となるものです。遺言書が残されていない相続では、協議したうえで相続人全員の合意を得ることができれば、自由な割合で遺産分割することが可能ですので、必ずしも法定相続分に従う必要はありません。
相続の花笑みでは、豊田にお住まいで相続に関するお悩みのある方に向けて、初回完全無料の相談会を実施しております。相続についての知識を経験を豊富に持つ専門家が、豊田の皆様の状況に合わせて適切にサポートさせていただきますので、豊田の皆様はぜひお気軽に相続の花笑みまでお問い合わせください。
2024年05月07日
Q:行政書士の先生、私の相続の際、前妻が相続人として財産を受け取ることは避けたいです。(豊田)
私は豊田在住の男性です。私の相続の際に誰が相続人になるのか知りたく、ご連絡いたしました。私は現在内縁の妻と共に豊田で暮らしています。子はおりません。10年ほど前に離婚した経験があり、前妻も豊田に住んでおります。前妻との間にも子はおりません。
前妻と離婚したきっかけは前妻の借金ですので、私の死後、私の財産を当てにしているのではないかと不安があります。行政書士の先生、私が亡くなった際に前妻が相続人となり、私の財産を受け取る可能性はありますか?できれば私の財産が前妻に渡るような事態は避けたいです。私の財産はすべて内縁の妻に渡したいと思っていますので、何か対応が必要であれば教えてください。
A:離婚した前妻が相続人となることはありませんのでご安心ください。
離婚した前妻の方には相続権がありませんので、ご相談者様の相続の際に相続人になることはありません。またお子様もいらっしゃらないため、前妻に関する人物にご相談者様の財産が相続されることはないでしょう。
民法では法定相続人(法的に相続権のある人)を以下のように定めています。
- 配偶者:常に相続人
- 第一順位:子(孫)…直系卑属
- 第二順位:父母(祖父母)…直系尊属
- 第三順位:兄弟姉妹…傍系血族
※配偶者は必ず法定相続人となります。そして第一順位の人が相続人となりますが、第一順位の該当者がいない場合は、第二順位の人が相続人となります。第二順位の該当者もいない場合は、第三順位の人が相続人となります。上位の順位に該当者がいる場合、それ以下の順位の人が相続人となることはありません。
上記にある「配偶者」は婚姻関係にある人ですので、現在豊田で同居されている内縁の奥様には相続権がないことになります。
もしも、ご相談者様の親族で第一順位~第三順位までのいずれかに該当する方がいらっしゃらない場合は、特別縁故者に対する相続財産分与の制度を利用して内縁の奥様が財産の一部を受け取れるかもしれません。この制度を利用する場合は、内縁の奥様が家庭裁判所へ申立てし、その申立てが認められてはじめて財産を受け取れるようになります。反対に言えば、申立てが認められない場合は財産を受け取れません。
このような事態にならないために、ご相談者様のほうで生前対策をしておきましょう。今回のようなケースで有効なのが遺言書の作成です。遺言書の中で内縁の奥様への遺贈を主張しておきましょう。その遺言書が法的に有効なものとするため、「公正証書遺言」という方法で遺言書を作成し、遺言書の中で「遺言執行者」を指定しておくと、遺言の実現がより確実なものとなります。
豊田にお住いの皆様、相続に関してご不安な点がありましたら相続の花笑みまでいつでもお問い合わせください。相続や遺言書に精通した経験豊富な行政書士が、豊田の皆様のお力になります。初回無料相談の場もご用意しておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
行政書士法人花笑みは愛知県の専門家です
0120-547-053
営業時間 9:00~19:00(土日祝も営業)

みよし市・豊田市・豊明市・日進市を中心とした愛知県中央エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談ください。