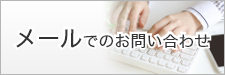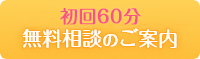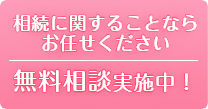地域
2026年02月02日
Q:母の遺産相続に際して、弟夫婦が遺産分割協議書を作成すべきだというのですが、なぜ作成すべきなのか行政書士の先生にお尋ねします。(豊田)
先日、母が豊田の自宅で亡くなりました。母と父はずいぶん前に離婚しておりますので、母の遺産相続では長女の私と、長男、次男の3人が相続人となります。
私は母の亡くなる日まで豊田の自宅で同居しておりましたので、豊田の自宅は私が遺産相続するとして、その他の預金や細々とした財産は偏りなく分け合うということで、遺産相続の方針は固まりました。
豊田の実家は名義変更などの遺産相続手続きが必要でしょうから、早速手続きに入ろうと思ったところ、次男夫婦が「遺産分割協議書を作成すべきだ」と言いだしました。
豊田の自宅を除けばそのほかの遺産はそれほど高額でもないし、みな遺産相続の方針に納得しているのだから、わざわざ書面を作成するほどのことでもないように思うのですが、次男の奥さんは過去に別の遺産相続で揉めに揉めた経験があるらしく、遺産分割協議書は必須だと言います。
行政書士の先生、相続人がみな遺産相続に納得していたとしても、遺産分割協議書は作成しなければならいのでしょうか。遺産分割協議書がなければ遺産相続の手続きができないというならば仕方ありませんが、そもそも何のために遺産分割協議書が必要なのか、教えていただけますか。(豊田)
A:遺産分割協議書は遺産相続のさまざまな手続きで活用されるうえ、相続トラブル回避にも貢献しますので、作成をおすすめいたします。
遺産分割協議書は、被相続人(亡くなった方)が遺言書を遺していない場合に作成する書面です。
もし遺言書があれば、その中に遺産分割に関する被相続人の遺志が記されていますので、原則としてその遺言書の内容をもとに遺産相続の手続きを進めます。そのため、相続人同士で遺産分割について話し合う必要はなく、遺産分割協議書の作成も不要です。
一方、遺言書のない遺産相続では、どの遺産を誰が取得するのか、相続人全員で話し合って決定する必要があります。この話し合いを「遺産分割協議」といい、この協議で決定した事項をまとめて書面にしたものが「遺産分割協議書」です。
遺産分割協議書は、遺産分割の内容を記載したうえで、相続人全員が署名し、実印を押すことで完成します。相続人全員の署名捺印がなされることで、遺産分割協議書は「遺産分割について相続人全員が合意している」と証明する法的な書面として扱われ、遺産相続手続きのさまざまな場面で活用できるようになります。
例えば、豊田のご実家をご相談者様が遺産相続するのであれば、相続登記の申請を行い、その名義を変更する必要があります。その際、遺産分割協議書を登記申請書と共に提示することになります。
ご状況によっては相続税の申告納税義務が生じる場合もありますが、そこでも遺産分割協議書が活用されます。
また、被相続人名義の銀行口座が複数ある場合、その遺産相続手続きの際に遺産分割協議書を持参すれば、銀行所定の相続届に相続人全員が毎回署名捺印する必要がなくなりますので、手間がかからずに済みます。
その都度相続人全員が署名捺印せずとも、遺産分割協議書を提示するだけで済むことを考えれば、あらかじめ遺産分割協議書を作成しておくことは十分メリットがあるのではないでしょうか。
弟様の奥様は過去の遺産相続で揉めた経験がおありのようですが、実際のところ、遺産相続は財産が動く手続きですので、相続人同士が衝突することも珍しいことではありません。遺産相続についてみな納得したと思っていても、後になって当初と異なる意見を主張されてトラブルになるケースもあります。あらかじめ遺産分割協議書を作成すれば、このような後々の遺産相続トラブルの回避に貢献すると考えられます。
遺産分割協議書は、遺産相続の手続きを円滑に進めること、ならびに今後の安心を確保することに役立ちますので、作成されることをおすすめいたします。
豊田の皆様、遺産相続にはさまざまな手続きが伴いますので、ご負担に感じることも多いかと存じます。相続の花笑みでは、豊田の皆様の遺産相続が円滑に完了するようお手伝いしております。豊田の皆様のご状況に応じて柔軟にサポートいたしますので、まずはお気軽に相続の花笑みの初回完全無料相談をご利用ください。
2026年01月06日
Q:母が亡くなったので相続手続きを進めたいのですが、準備すべき戸籍について、行政書士の先生に教えていただきたい。(豊田)
豊田で一人暮らしをしていた母が亡くなりました。姉妹で協力して相続手続きを進めたいと思ってはいるのですが、戸籍の部分でつまづいています。銀行で母の口座に関する手続きをしたいと思うのですが、亡くなった母の戸籍が足りないといわれてしまい、相続手続きができませんでした。
行政書士の先生、相続手続きのためにはどのような戸籍を準備すればよいのでしょうか?準備すべき書類が多くて混乱しています。 (豊田)
A:被相続人の戸籍は「出生から死亡までの連続した戸籍」、相続人は「現在の戸籍」をご準備ください。
相続手続きのために準備すべき戸籍は、主に以下のものです。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)
- 相続人の現在の戸籍謄本(相続人全員分)
これらの戸籍を準備すれば、被相続人の配偶者や子の有無、兄弟やご両親の情報などをすべて読み取ることができます。これにより、今回の相続で誰が相続人になるのかを明確にすることができ、相続手続きを進めるうえでは相続人を第三者に証明するための重要な書面となるのです。それゆえ、銀行などで相続手続きを進める際には提出が求められます。
戸籍には養子や認知している子などの情報も記されますので、戸籍を収集することで思わぬ相続人の存在が発覚する可能性もゼロではありません。相続が発生した際はお早めに戸籍収集に取りかかるようにしましょう。
なお、2024年3月から「戸籍の広域交付制度」が開始され、一か所の市区町村窓口で複数の戸籍証明書等を請求できるようになりました。ご本人および配偶者・子・父母などであれば戸籍の広域交付制度を利用できます。
戸籍には種類がありますし、相続手続きでは戸籍に限らず他にも数多くの書類を扱うことになります。相続に不慣れな方にとっては非常に負担の大きい作業となりますので、相続の専門家に対応を依頼することもご検討いただければと思います。
相続の花笑みは相続の専門家として、豊田の皆様の相続手続きや遺言書の作成、生前対策など、さまざまなお手伝いをしております。これまで培った豊富な知識とノウハウを強みに、豊田の皆様の相続手続きが滞りなく進むようしっかりとサポートさせていただきますので、豊田で相続に関するお悩みをお持ちの方はぜひ相続の花笑みへご相談ください。
初回のご相談は完全無料です。豊田の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。
2025年12月02日
Q:行政書士の先生、遺産相続の手続きはどのように進めればよいですか?(豊田)
豊田で長年連れ添った夫が亡くなったのですが、遺産相続のことで困っています。私は役所などでの手続きがとにかく苦手で、これまでも何か手続きが必要な時には夫に頼りきりでした。その夫が亡くなってしまったので、夫の遺産相続手続きは私がやるしかありません。何からはじめればよいのかまるで見当もつかず途方に暮れていたところ、こちらの事務所が遺産相続に強いと聞いてご連絡させていただきました。
行政書士の先生、遺産相続の手続きはどのように進めればよいか、教えていただけますでしょうか。(豊田)
A:遺産相続の流れをご説明しますが、専門家が手続きを代行することもできますのでいつでもご相談ください。
相続の花笑みにお問い合わせいただきありがとうございます。
人はいつか亡くなるものと分かってはいても、いざ大切な方を失うとどうすればよいのかわからず途方に暮れてしまう方も少なくありません。遺産相続の手続きは複雑で手間のかかるものもありますが、遺産相続の専門家が代わりにご対応することも可能ですので、どうぞご安心ください。
まずはお亡くなりになった方(以下、被相続人といいます)が遺言書を遺されていないか確認しましょう。遺産相続において被相続人の最終意思が記された遺言書は何よりも優先されます。豊田のご自宅で遺品整理される際に遺言書の有無を必ずご確認ください。
遺言書が無い場合には、以下の流れで遺産相続手続きを進めていきます。
1.必要な戸籍を収集し、相続人を確定する
相続人が誰なのかを明確にするため、被相続人のお生まれから亡くなるまでの連続した戸籍をすべて集めます。同時進行で相続人の現在の戸籍謄本も取り寄せておきましょう。
2.相続財産を調査する
被相続人が生前のどのような財産を所有していたのか調べます。遺産相続では現金や不動産などのプラス財産はもちろん、借金や住宅ローンといったマイナス財産も相続人が引き継ぐことになります。
豊田のお住まいが持ち家であれば、その登記事項証明書や固定資産税の納税通知書など、預貯金については口座の通帳や残高証明書などを用意しましょう。用意した書類をもとに相続財産目録を作成します。
3.相続するかしないかを決める
相続人には相続放棄の権利があります。遺産相続するのか、それとも放棄するのか、はたまたプラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を引き継ぐのか(限定承認という方法です)、相続人の意思で決めます。相続放棄や限定承認を選ぶのであれば、“自己のために相続が発生したことを知った日から3か月以内”に手続きが必要です。
4.遺産分割を行う
相続人が複数名いる場合には、遺産相続の対象となる財産を、誰がどの程度引き継ぐのかを相続人全員で話し合って決める必要があります。この話し合いを遺産分割協議といいます。協議で相続人全員が合意した内容は、遺産分割協議書として書き起こし、相続人全員で署名捺印します。
5.遺産相続した財産の名義変更を行う
不動産など名義の変更が必要な財産については、引き継ぐことになった人の名義へと変更する手続きを行いましょう。
以上が簡単な流れですが、遺産相続の手続きはご家庭の状況や財産の内容などによって行うべき手続きが異なってくることもありますのでお気をつけください。
相続・遺言を専門に扱う相続の花笑みでは、豊田の皆様に向けて初回完全無料の遺産相続に関するご相談会を実施しております。豊田の皆様のお話を丁寧にお伺いしたうえで、これから行うべき遺産相続の手続きの流れを分かりやすくご案内させていただきます。豊田の皆様はどうぞお気軽に相続の花笑みの遺産相続無料相談をご利用ください。
行政書士法人花笑みは愛知県の専門家です
0120-547-053
営業時間 9:00~19:00(土日祝も営業)

みよし市・豊田市・豊明市・日進市を中心とした愛知県中央エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談ください。